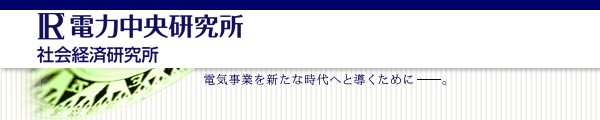
経済・エネルギー需給の将来展望には人口がどうなるかを見極める必要がある。
以下では、2025年までの人口展望の概要を紹介したい。
1. 避けられない少子・高齢化と人口減少
国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2002)によれば、日本の総人口は今後数年以内にピークを迎える。少子化が加速し、1970年代後半以降、合計特殊出生率(一人の女性が生涯に生む子供の数の指標)が人口維持水準2.08を大きく下まわり、その影響が現れ始めるためである。国立社会保障・人口問題研究所推計は、唯一の公的な将来推計値であるが、5年に一度しか公表されないことや、地域別世帯数については、推計結果の公表がかなり遅れるため、当所では、独自に人口予測モデルを開発し、これを使って地域別の人口及び世帯数を推計している。
各地域の人口水準を求めるためには、年齢階層別に死亡率、地域間人口移動及び出生数を求めて推計する。死亡率は地域間格差が縮小してきたのに対し、出生率にはかなりの地域差がみられる。その要因としては、近年、我が国では社会保障や医療サービスが全国的に充実し、生活習慣が均一化したことで、生残率の地域差はなくなってきているが、初婚年齢や出生行動、地域間人口移動については、経済社会的な要因が地域差をもたらしていると考えられる。2025年までの出生率をみると、初婚年齢の上昇、晩産化の進展から30歳代の出生率は若干上昇するものの、20歳代の出生率が低下し、これが社会全体の出生率(TFR)を引き下げる(図1)。
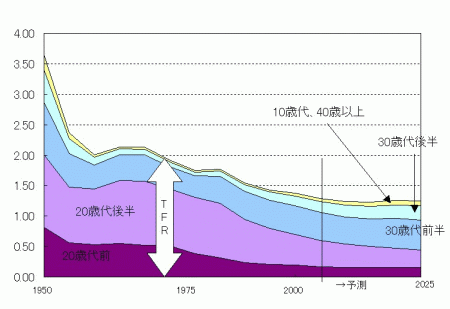
図1 合計特殊出生率(年齢階層別,2002年以降は予測)
2. 数年以内に全ての地域の人口は減少する
地域の人口は自然増減(地域内出生数-死亡数)と社会増減(地域間人口移動、国外との移動)で決まる。今回の展望では、全国総人口の減少は2006年から始まると推計されたが(図2)、男女別あるいは地域別にみると地方圏の男性が最も早い段階でピークを迎え、次いで地方圏の女性、大都市圏の男性、そして最後に大都市圏の女性人口が減少局面に入る。2008年には全ての地域で自然減少に陥り、予測期間の後期にかけ、平均寿命を越える世代の人口が年々増加していくことから、各地域の人口減少数は拡大していくとみられる。
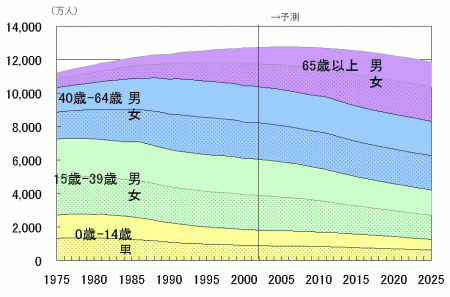
図2 男女・4年齢階層別人口の推移
出所:実績値は国勢調査、厚生省10月1日人口。
特に出生率の低い北海道、首都圏、関西では、自然減少要因による総人口の減少の影響は大きくなっていくと考えられる。また、大都市圏では、人口規模が大きいだけに、人口減少数も大きい。2024〜2025年でみると首都圏では、約30万人、中部、関西では約10万人もの人口純減になると推計された。これは、毎年数個の中規模都市が消滅していくのと同様なインパクトを大都市圏の経済社会に与えていく。
また人口構造の高齢化に伴い、当然ながら高齢世帯も増加していく。世帯主が65歳以上世帯の比率は、2000年の24%が2025年の37%に上昇する。地域別にみると2000年の首都圏20%〜四国30%が、2025年の首都圏36%〜四国41%にまで上昇し、大都市圏で高齢者世帯比率が急上昇する。このような高齢者世帯の増加は、エネルギー需要や最終消費支出の構造を大きく変えていくとみられる。
3. 地域間人口移動者数は収束へ
地域別人口を展望する際には、出生行動、死亡者数の動向に加え、地域間人口移動を捉える必要がある。若年人口の減少に伴い、総移動者数は減少していくと考えられるが、1970年代後半から続いて来た北関東、首都圏や中部への転入超過傾向は依然として継続していくとみられる。この要因を男女別にわけて比較すると、これらの地域への社会純流入の要因は異なっている。首都圏や中部では、男性比率の高い業種(製造業、公務員)の就業者需要の伸び率が他地域に比べ高く推移するとみられることから、相対的に雇用機会が拡大し純流入の傾向が続くとみられる。
一方、男性に比べ移動率そのものは小さいものの、女性の地域間人口移動における首都圏への一極集中は著しい。90年代半ば以降は、転入超過がみられるのは首都圏のみであった。これは、男女の就業比率がほぼ等しいサービス産業が首都圏で集積していることと、不況下で地方圏の雇用機会が減少していたことの両面が考えられる。今後も経済のサービス化が続くとみられることから首都圏での純流入傾向は続くとみられる。
4. 労働力人口の確保
1990年代初頭に70%でピークをつけた生産年齢人口(15〜64歳)の総人口に占める割合は、2000年には60%、2025年には51%へと低下していくとみられる。労働力人口の減少が当然ながら予想され、その要因は2025年までの展望期間の前半と後半では異なる。2015年頃までは、団塊の世代の引退により労働者数が減少し、それ以降は少子化による若年人口の伸び悩みによる労働力の供給不足問題が発生する。
2002年の各地域の男女・年齢階層別有業率(就業構造基本調査、図3)が今後も継続すると仮定すると、2025年には就業者数は約5,400万人になり、1970年代中頃の水準にまで低下する。この場合、就業者の総人口に占める割合は、2000年の50%から2025年の45%になる。
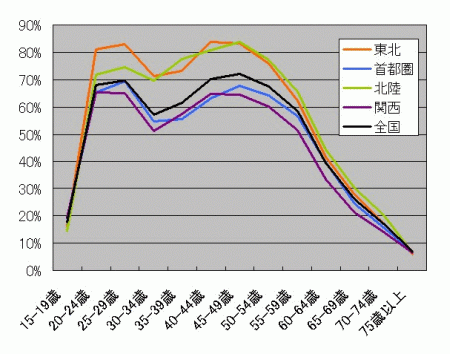
図3 女性有業率 (2002年就業構造基本調査)
団塊の世代が労働力市場から引退をはじめる2010年以降の就業者数の急激な減少を抑えるには、現時点で有業率の低い、30歳代以上の女性及び高齢者の有業率を高める対策が考えられる。ただし、ワークシェアリングなどを積極的に導入するとしても高齢者の雇用者増には限界があると考えられるため、大都市圏の女性有業率を高めることがひとつの解決策となる。労働需要を作り出せたらという前提が必要だが、例えば、2002年に全ての地域の男性高齢者と女性の全年齢階層の有業率が、北陸地域の水準になったとすると実に700万人近い労働供給の増加が見込まれる。
政策手段として実際の有効性には議論の余地はあるが、職住が近接させる環境の整備、保育サービスの充実、不妊治療への補助金交付などの少子化対策が、近年、国会を含め、様々な場で論議されている。当然ながら出生数の動向は、年齢階層別の出生率だけでなく既存の人口構成のパターンにも左右される。今後、出生率が一定あるいは若干の改善がみられたとしても、既に団塊ジュニア世代は結婚・出産の適齢期を迎えていることから、出生数の低下は避けられない。将来の人口・労働供給の減少ショックを少しでも緩和するためには、早急な少子化対策と働きながら子育てのできる環境の整備が求められる。
(社会経済研究所 主任研究員 山野紀彦)
